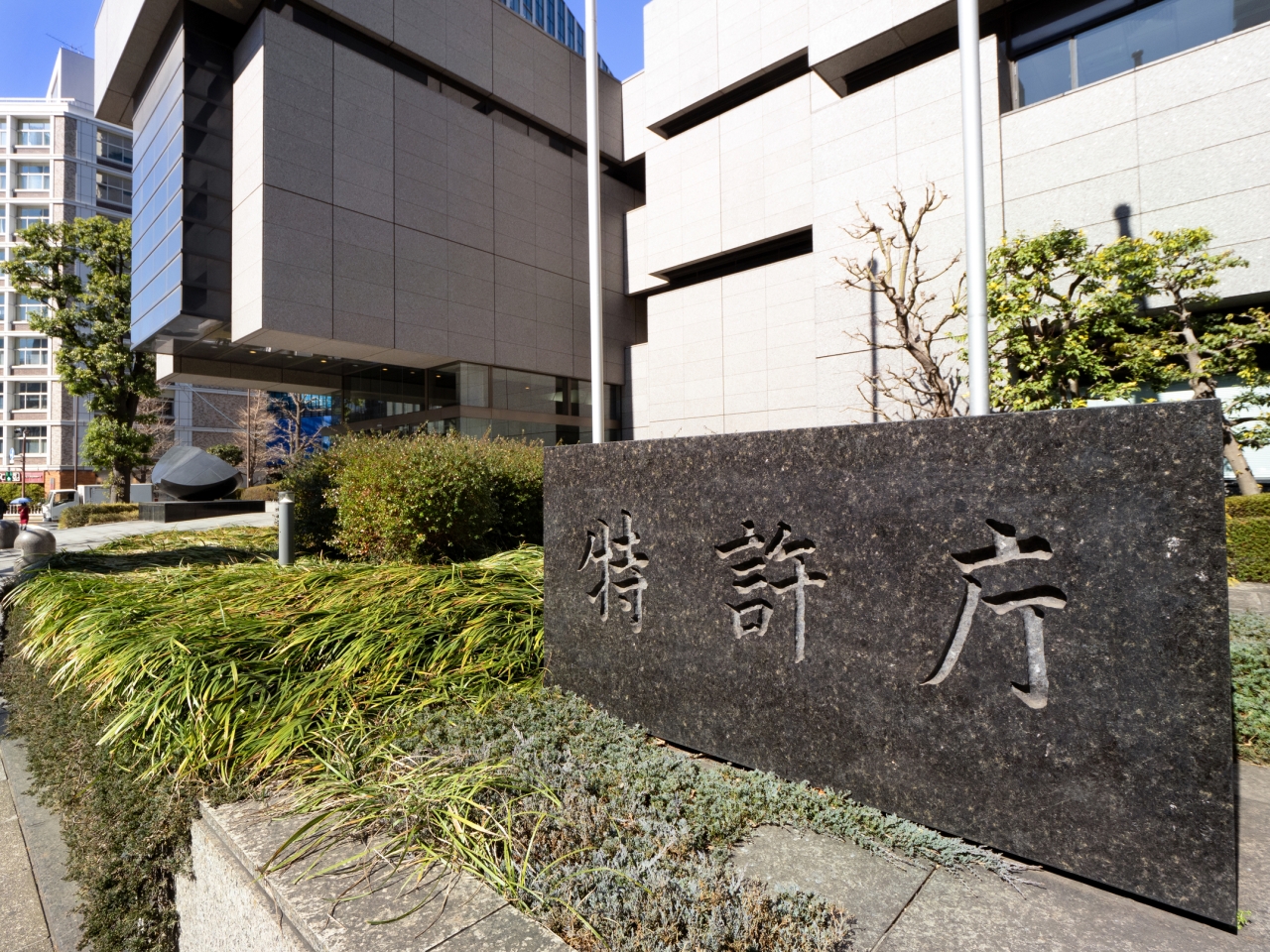経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
1 過労自殺に関する統計資料と最近の報道事例等
「令和5年版過労死等防止対策白書」(厚生労働省)によると、令和4年の自殺者数は 21,881 人と前年より874人増加し、そのうち勤務問題を原因・動機の1つとする自殺者の数は2,968 人と一定の割合を占めています。
2022年5月には、神戸市の病院の男性医師が長時間労働の末に自殺をしたニュースがSNS等で大きな注目を集め、広く報道されました。この事件に関しては、2023年6月に西宮労働基準監督署より労災認定がなされています。
また、2024年3月には、造船会社に勤務していた男性社員が、3年前、海外赴任先のタイで自殺したのは慣れない業務による負担や上司の厳しい指導などで精神疾患を発症したことが原因だとして労災認定された旨の報道がなされ、この事件についても大きな注目を集めました。
前回のコラム(※)で解説をしたとおり、企業には従業員の過労自殺についても防止をするための積極的な取り組み・仕組みづくりが求められます。
(※) 「従業員の過労死を防ぐために~企業に求められる取り組み~」はこちら
今回のコラムでは、どのような場合に過労自殺が労災とされるのか、過労自殺の労災認定基準について確認をしたうえで、過労自殺について使用者等の責任を認めた裁判例と企業に求められる対策について概要を説明していきます。
2 過労自殺の労災認定基準
まず、過労自殺とは、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡をいいます。過労自殺の労災認定基準については、以下の3つの要件を満たす必要があるとされています。
まず、①の対象となる精神障害は、世界保健機関(WHO)が勧告する「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」第10 回改訂分類(ICD-10)第Ⅴ章によって定められており、うつ病や急性ストレス反応などが該当します。
次に、②として対象疾病の発症前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷があったことが必要とされます。具体的には、認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」を基に出来事の心理的負荷の強度を「弱」、「中」、「強」の三段階で評価し、総合評価が「強」と判断される必要があります。評価表では、具体的出来事として「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」ことも明記されおり、また、パワーハラスメントの相談を受けた使用者側の対応についても心理的負荷の程度の評価において考慮するとされています。
そして、上記①及び②を満たす場合、認定基準の別表2「業務以外の心理的負荷評価表」を基に③業務以外の心理的負荷及び本人の個性によって当該精神障害を発症したものではないことについて判断することになります。
厚生労働省「精神障害の労災認定」10頁より引用
なお、労災保険法では、労働者の故意による負傷、疾病、障害、死亡については保険給付を行わないとしているため(同法12条の2の2第1項)、自殺の場合は保険給付が行われないのではないか問題となります。この点について、認定基準では、業務によりうつ病や急性ストレス反応などの特定の精神障害を発病したと認められる者が自殺を図った場合、精神障害によって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったものと推定し、「故意」ではないとされています(上記フローチャートの認定要件①カッコ書きを参照)。
3 過労自殺と使用者の安全配慮義務
過労死の場合と同様に、過労自殺について労災認定がなされた場合でも、すべての損害が補償されるわけではないため、補償されない損害については、遺族から企業等に対し損害賠償請求が行われることになります。
過労自殺について使用者の安全配慮義務違反を認めた裁判例としては、いわゆる電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)があります。新入社員の男性が慢性的な長時間労働に従事していたところ、うつ病に罹患し自殺するに至ったことから、遺族が会社に対して損害賠償請求をした事案です。
最高裁は、まず「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当である」としました。そして、「使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである」としたうえで、男性の上司らは、男性が恒常的に著しい長時間労働に従事していること及びその健康状態が悪化していることを認識しながら、その負担を軽減させるような措置を取らなかったとして、会社の安全配慮義務違反を認めました(その後、会社が約1億6,800万円を支払うとの内容で和解が成立しています)。
上記最高裁判決以降も、たとえば、比較的最近の過労自殺に関する裁判例として、以下の事例等を挙げることができます。
大阪地裁令和5年4月18日判決 |
・配管工事会社の男性従業員が自殺したのは、30日間連続で勤務するなど長時間労働によるうつ病が原因であるとして、遺族が会社に損害賠償を求めた訴訟。男性は2017年4月に大阪市から単身赴任し、東京都内の配管工事の現場監督として勤務。通常4カ月かかる工程を2カ月で行うよう指示され業務量が増え、月138時間の時間外労働を行い、8月下旬にうつ病を発症し、同年9月に自宅アパートで自殺した。 ・裁判所は、「(会社側は)労働者の心身の健康を損なうことがないように注意すべきだったのに怠った」として、自殺との因果関係を認め、約4400万円の支払いを命じた。 |
これらの裁判例からもわかるように、従業員の恒常的な長時間労働や健康状態の悪化を認識した場合、企業には速やかにその負担を軽減させるなどの措置を講ずることが求められます。
4 メンタルヘスルケアを念頭においた休職制度の整備
従業員の過労自殺を防ぐために企業に求められる取り組みは、過労死を防ぐための取り組みと同様に、①長時間労働の削減、②働き方の見直し、③メンタルへルスケア対策、④職場のハラスメントの防止が基本となりますが、中でも従業員の③メンタルヘルスケア対策に関する取り組み・仕組みづくりが特に重要となります。
その際、実務的に見落としがちなのが私傷病休職制度の整備です。私傷病休職制度については、法律上制度を設ける義務はなく、設置の有無や制度の内容は会社の判断に委ねられています。そのため、特に中小企業等においては、制度自体が就業規則から漏れてしまっていたり、あるいは制度としては規定されているものの、休職の要件や期間、休職期間中の処遇、経過報告等の義務、復職の要件等について欠けてしまっていたり、十分な内容となっていないケースが散見されます。
休職制度を設け、上記の点を含め事前にルールづくりをしておかないと、従業員のメンタル不調に早期に気づけた場合でも、医師の診断を受けさせたり、休ませるなどの適切な対応ができなかったり、復職に際して会社と従業員とで意見の違いが生じ、トラブルとなってしまうことがあります。
過労自殺に関しては、前述した訴訟リスクに加え、報道を機にSNS等において拡散され、社会的な非難を受けることも多いため、企業のレピュテーション(信用)にも大きな影響を及ぼす点に留意し、上記の各種施策を実施する必要があります。
今回のコラムを機に、自社の私傷病休職制度を含め、従業員のメンタルヘルスケアに関して十分な体制を構築できているか、今一度、確認をしてみてください。
(このコラムの内容は、令和6年6月現在の法令等を前提にしております)
(執筆)五常総合法律事務所
弁護士 持田 大輔
MKT-2024-512
「ここから変える。」メールマガジン
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事