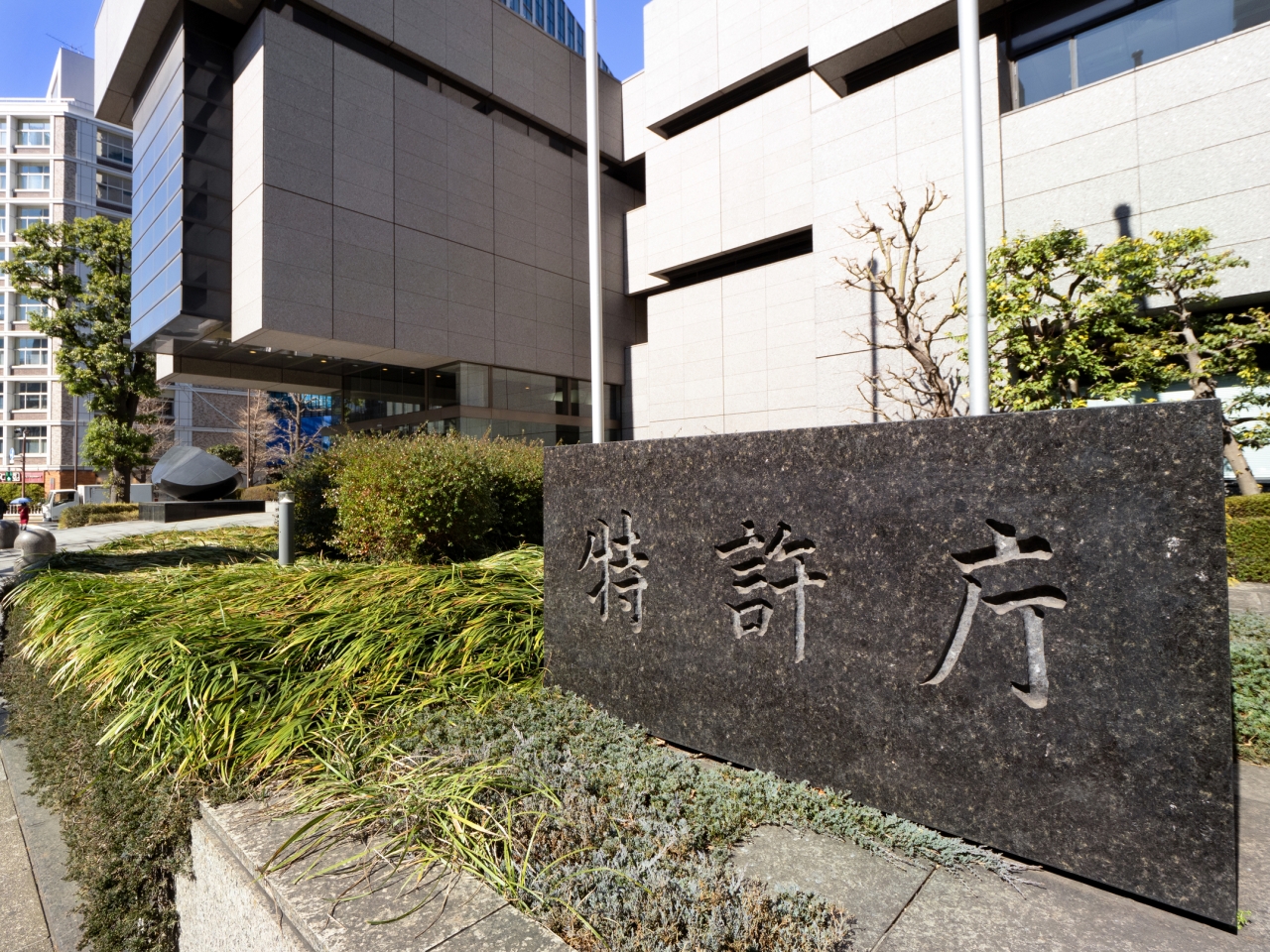気候変動は地球全体の気候が変化する現象で、その原因には人類の産業活動が深く関わっているといわれています。気候変動は急激な気温の上昇や下降を招き、洪水や渇水、冷害といった自然災害の原因となるほか、熱中症や疫病の流行などによる死者の増加など、地球上の生命への影響も計り知れません。
気候変動は企業に対しても、施設の損壊や従業員への健康被害など、事業活動に影響をもたらす可能性があります。
こうした気候変動に対し、企業はどのように向き合えばいいのでしょうか。ここでは、気候変動の原因から企業への影響を解説するほか、実際に取り組まれている対策事例を紹介します。
気候変動とは長期的な気候パターンの変化のこと
気候変動とは、地球全体の気候が長期的に変化する現象を指します。
具体的には、平均気温の上昇または下降、降水パターンの変化、海面水位の上昇または下降、極端な気象現象の増加などです。
なお、国連総会で採択された条約では、気候変動を「地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるもの」と定義しています。つまり国連の定義では、自然による変化(自然要因)に追加して、人間による活動が原因となっている部分について、特に気候変動といっています。
出典:「気候変動に関する国際連合枠組条約」(環境省)
気候変動の原因
国連の定義では、気候変動を人間活動が原因であることを強調していますが、一般的に気候変動の原因は、宇宙規模で起きる自然要因と人間活動による人為的要因の2つに分類されます。
それぞれの違いは以下のとおりです。
自然要因
自然要因とは、人間活動とは関係なく、地球や宇宙の自然な変動によって引き起こされる原因のことです。
主な自然要因には、太陽の活動の変化、火山の噴火、地球の自転軸の傾きの変化などがあります。
人為的要因
人為的要因とは、人間活動によって引き起こされる原因のことです。国連の定義にもあるように、現在問題となっている気候変動の多くが、この人為的要因が原因であるといわれています。
主な人為的要因には、温室効果ガスの排出、森林破壊、産業活動などがあります。
温室効果ガスとは、二酸化炭素(CO2)、メタン、一酸化二窒素、代替フロンなどがあり、産業革命以降、人類が排出し続けているガスです。特に、大気中のCO2濃度は上昇し続け、気候変動の一部である地球温暖化の一因となっています。
異常気象や地球温暖化との違い
気候変動と似た言葉に異常気象や地球温暖化があります。これらの言葉が、気候変動とはどのように異なるのか解説します。
異常気象
異常気象は、数十年に1回あるかないかという、誰も経験していないような気象の変化を指します。
気象の変化には、数時間にわたって起きる大雨や暴風、極端な冷夏・暖冬などがあり、気象庁では30年に1回以下で発生する現象としています。
これに対し気候変動は数十年や数百年など、より長期的にわたって起きている気候の変化のことです。
引用:「気候・異常気象について」(気象庁)
地球温暖化
地球温暖化は、気候変動の一部であり、地球の平均気温や地表、海水温が長期的に上昇する現象を指します。一方、気候変動は、温暖化以外にも寒冷化なども含む気候全体の変化のことです。
近年は温暖化が問題となることが多いため、一般的に気候変動というと、地球温暖化を指す場合が多くあります。
地球温暖化の主な原因としていわれているのは、人間の活動に伴って発生する温室効果ガスです。温室効果ガスが大量に排出されることで、大気中の温室効果ガスの濃度が増加し、地表や大気に加え、海水の温度も上昇させています。
温室効果ガスが地球温暖化につながる仕組みは下記のとおりです。
■地球温暖化のメカニズム
気候変動が企業にもたらす影響
では、気候変動によって、企業の事業活動にどのような影響がもたらされるのでしょうか。主に、次のような影響があると考えられています。
施設や設備の物理的損害
気候変動による大雨や洪水などの自然災害が、企業の施設や設備に物理的な損害をもたらす可能性があります。施設が破壊されるなど被害の規模が大きい場合、事業が継続できず、長期的に中断せざるをえない事態も懸念されます。
サプライチェーンの停滞
気候変動の影響が港湾や道路、鉄道などの輸送インフラに及ぶと、サプライチェーンの混乱や寸断が起きる可能性が高まります。例えば、台風により輸送が止まり、製品や原材料の供給に遅延が発生することが気候変動により頻発すると、国際的なサプライチェーンを持つ企業は深刻な納期遅延やコスト増加のリスクに直面することになるでしょう。
従業員への健康被害
気候変動の影響により、熱中症や感染症による健康リスクの増加が懸念されます。農業や建設業など屋外労働者の多い職場では、特に注意が必要です。
資源の不足とコストの増加
気候変動の影響は資源の不足とコストの増加を招きます。資源不足は原材料の価格上昇につながり、企業の生産コストを押し上げる要因になるでしょう。
市場ニーズの変化
気候変動が市場のニーズにも影響を与える可能性があります。
例えば、温室効果ガスの削減を目指す社会になると、化石燃料を使用する商品やサービスへの需要が弱まるといったニーズの変化が考えられます。化石燃料を使用した商品をメインの事業としている場合は、方針転換を余儀なくされるかもしれません。
気候変動に対する企業の取り組み
気候変動は、地球規模での深刻な課題であり、企業は地球環境を守るための具体的な行動を取ることが重要です。企業が気候変動対策に取り組むことは、気候変動の抑制につながり、その結果として企業自体にもさまざまなメリットがもたらされる可能性があります。
ここでは、気候変動対策に対する企業の取り組みについて解説します。
環境にやさしい商品やサービスの開発をする
気候変動対策として、環境にやさしい商品やサービスを提供する方法があります。例えば、脱炭素社会に向けて化石燃料を使用しない製品や、リサイクル可能な資材を使った商品の開発などです。
このような取り組みは、温室効果ガスの削減や自然資源の保全につながり、持続可能な社会を実現するための重要な役割を果たします。結果として、環境への配慮が評価され、新市場への参入や収益の拡大につながる可能性があります。
再生可能エネルギーを導入する
企業が再生可能エネルギーの導入することも、気候変動対策の取り組みのひとつといえます。
企業活動でESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する取り組みを積極的に行えば、地球環境に好影響をもたらすほか、投資家や金融機関からも評価され、資金調達しやすくなるといったことにもつながるでしょう。
なお、再生可能エネルギーは初期投資コストが高めですが、運用コストは低めであり、技術の進歩とともにコストは削減されるという見方があります。長期的にはエネルギーコストの削減も見込めます。
温室効果ガスの排出量削減に取り組む
気候変動対策として企業が温室効果ガスの排出量削減に取り組むことは、企業の社会的責任(CSR)を果たす一環であり、地球温暖化の防止に直接的な貢献を果たすことになります。
例えば、企業が森林保全プロジェクトに参加し、森林による温室効果ガスの吸収量を増やしたり、事業活動における省エネルギー化の推進に取り組んだりすることで、温室効果ガスの削減を図れるでしょう。また、これらの活動が企業の信頼性やブランドイメージの向上につながり、顧客のロイヤルティや企業価値が高まる可能性もあります。
気候変動対策には「緩和」と「適応」が重要
企業による気候変動対策には、「緩和」と「適応」の2つのアプローチが必要とされています。
緩和は気候変動の原因となる地球温暖化を抑制する対策です。温室効果ガスの排出を減らすというアプローチで、緩和策ともいいます。
適応は、すでに起こりつつある、あるいは将来予測されるリスクに備える対策です。気候変動による被害を軽減する、もしくはなくすというアプローチで、適応策ともいいます。
緩和策によるアプローチを最大限に実施したとしても避けられない気候変動の影響に対し、被害をできるだけ軽減し、よりよい生活ができるようにしていくための取り組みが適応策といえます。
企業は、このどちらかだけを行えばよいというわけではなく、緩和策と適応策の両方を行っていくことが重要です。
■主な緩和策
緩和策の例 |
内容 |
温室効果ガスの排出削減 |
エネルギー効率の改善や省エネルギー技術の導入により、企業活動における温室効果ガスの排出の削減を目指す |
再生可能エネルギーの利用 |
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを積極的に導入し、化石燃料への依存を減らす |
森林保護と植林 |
二酸化炭素を吸収する森林の保護や新たな植林活動を行う |
循環型経済の推進 |
リサイクルや再利用を促進し、資源の効率的な利用を図る |
■主な適応策
適応策の例 |
内容 |
耐久性のあるインフラ整備 |
気候変動による極端な気象現象に耐えられるよう、建物や道路などのインフラを強化する |
水資源管理 |
干ばつや洪水に備えて、効率的な水の利用と貯水システムの整備を行う |
農業の適応 |
高温でも育つ農作物など、気候変動に適した作物品種の開発や栽培方法の変更を行う |
健康対策 |
熱中症予防や感染症対策など、気候変動がもたらす健康リスクに対応する |
企業が取り組んでいる適応策の例
気候変動に対して緩和策と適応策の両方を行うことが重要ですが、気温上昇に伴う自然災害は、直近で起こることが想定されます。ここでは、実際に企業が取り組んでいる適応策の例を紹介します。
洪水対策
気候変動に伴う洪水の適応策として、災害を想定した設備の配置変更や専用設備の導入などが実施されています。
例えば、配電盤など工場の操業に重要な機械を、洪水に備えて最初から高層階に設置するといった対策です。また、河川が近い企業では、水害対策として雨量によって警報メールを配信するシステムを開発しているところもあります。
従業員の安全・健康対策
気候変動によって増大する、従業員への健康リスクへの対策も不可欠です。
熱中症などの疾病を未然に防ぐために腕時計型センサーを使い、作業現場の従業員の健康状態を常時モニタリングしたり、日射を避ける休憩場所や環境センサーを設置したりするなどの取り組みを進めている企業もあります。
サプライチェーン分断への対策
気候変動による水害などにより、サプライチェーンが分断されることを想定した適応策を講じる企業もあります。
リスクの高い原材料について世界各地の調達先を複数確保し、代替材料の検討に取り組んだり、原料農産物について、気候変動に適応した新品種の開発に積極的に取り組んだりしている例もあります。
中小企業支援機関による脱炭素化のサポート
経済産業省は、中小企業の脱炭素化を推進するため、「カーボンニュートラル・アクションプラン」を策定しています。
このプランは、中小企業団体や金融機関などの支援機関が策定し、中小企業の後押しをする施策です。支援機関は、省エネ・温暖化対策に関する情報提供、相談対応、セミナーの開催、経営指導員の研修などを行い、中小企業の具体的な行動をサポートします。
気候変動の対策をしたくてもどこに相談してよいかわからない場合に、強い味方となってくれるでしょう。
出典:「中小企業支援機関によるカーボンニュートラル・アクションプラン」(経済産業省)
気候変動の原因を認識し、企業ができる緩和策・適応策に取り組もう
社会や人々の暮らしに大きな影響を与える気候変動は、国だけでなく企業にとっても対策をすることが不可欠な現象です。気候変動の原因が人間活動にあることを認識し、企業の在り方を考える段階といえます。
企業は温室効果ガス削減など緩和策の実施に加えて、気候変動の影響に備える適応策にも取り組む必要があります。気候変動対策を企業の存続と競争力を高める重要な投資として捉えて、着実に推進していくことが大切です。
経済産業省の「カーボンニュートラル・アクションプラン」などを活用して取り組んでみてはいかがでしょうか。
MKT-2025-506
「ここから変える。」メールマガジン
経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事