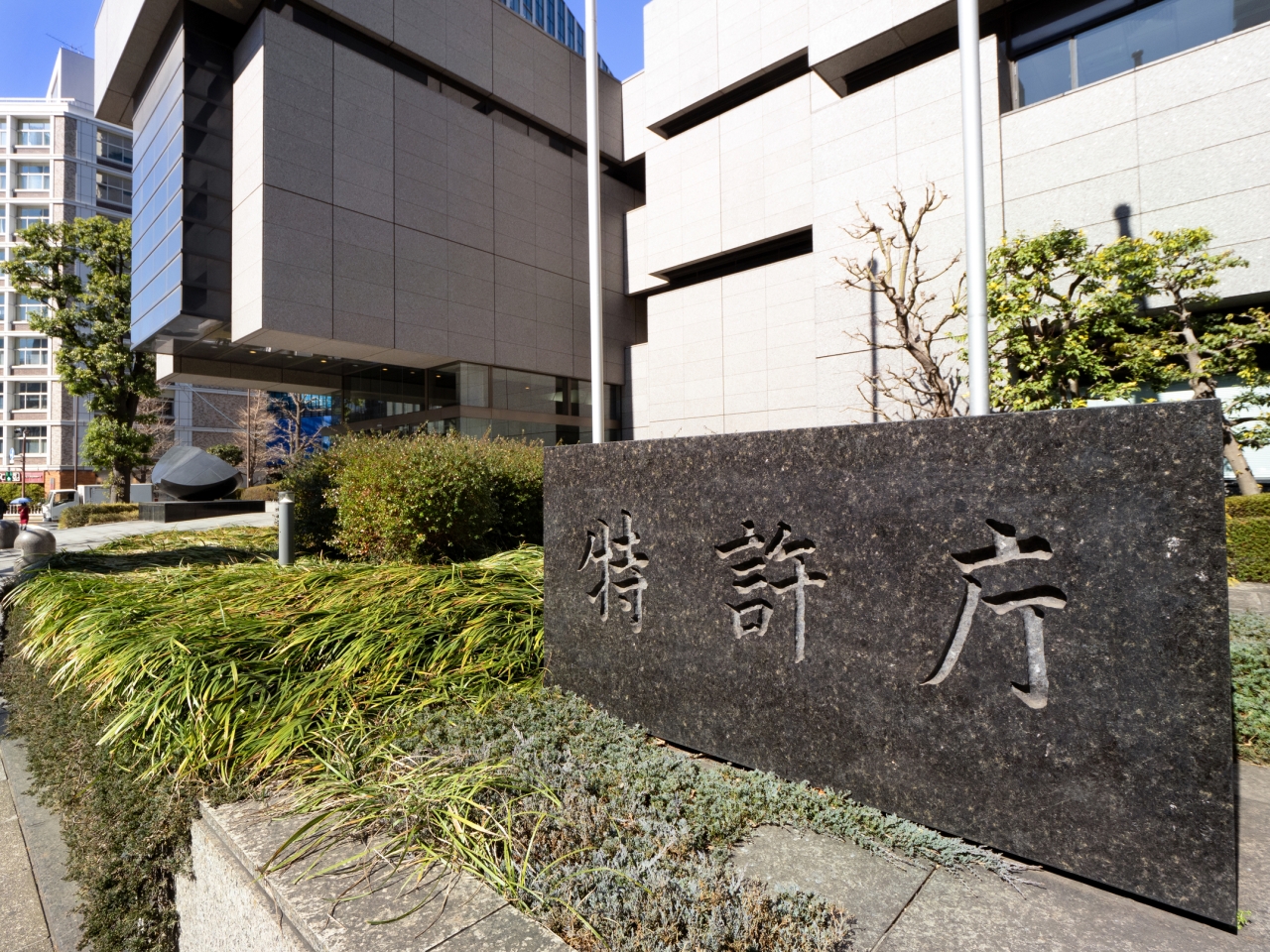-
リテラシーとは、情報を理解し適切に活用する能力のこと -
リテラシーが使われる用語や例文 -
ITリテラシーが低い場合のデメリット -
中小企業のデジタル化の現状 -
中小企業におけるITリテラシーの高め方 -
中小企業もリテラシーを高める取り組みを積極的に行おう
「リテラシーを高める」「ITリテラシーが低い」など、リテラシーという言葉を使う機会が増えています。しかし、中には正確な意味を理解しないまま使っていたり、ビジネスにおいて間違った使い方をしていたりする人も多いのではないでしょうか。
ここでは、リテラシーの意味やリテラシーがよく使われる用語について解説します。また、中小企業に重要なITリテラシーに焦点を当て、ITリテラシーが低い場合のデメリットや、中小企業におけるデジタル化の現状およびITリテラシーの高め方などを取り上げます。
リテラシーとは、情報を理解し適切に活用する能力のこと
リテラシーの本来の意味は、「読み書きの能力」です。ただ現在では、「その分野についての知識」や「その分野に関する能力を活用する力」を指すのが一般的です。
特にビジネスシーンでは、「その分野の情報を正しく理解して活用する能力」という意味合いで使われることが多く、業種によっては該当するリテラシーの高さが求められます。
リテラシーが使われる用語や例文
リテラシーはITリテラシーやメディアリテラシーなど、さまざまな分野で用いられます。ここでは、ビジネスでよく使われるリテラシーを使った用語と例文を、5つピックアップして解説します。
ITリテラシー
ITリテラシーとは、IT機器やサービス、IT関連の情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のことです。パソコンの使い方やソフトの操作方法だけでなく、「ビジネス上の課題を解決するためにITを活用する能力」、「ITツールを使って業務を効率的に進める能力」といった意味合いも含まれます。また近年では、ITリテラシーの中でも「情報セキュリティに関するリテラシー」が重要視されつつあります。
ITリテラシーは、さらに「情報基礎リテラシー」「コンピューターリテラシー」「インターネットリテラシー」などに細分化されます。
ITリテラシーを使った例文は次のとおりです。
<ITリテラシーを使った例文>
「OSやアプリケーションの定期的なアップデートの重要性を理解している社員は、ITリテラシーが高いといえる」
「ITリテラシーが不足していると、フィッシングメールに引っかかる可能性が高まる」
ビジネスリテラシー
ビジネスリテラシーとは、ビジネスの現場で全般的に必要とされる能力や知識のことです。名刺交換や挨拶の作法など基礎的なことも含みますが、近年では論理的思考力やコミュニケーション能力、課題解決のための能力などを指すことが多くなっています。
ビジネスリテラシーを使った例文は次のとおりです。
<ビジネスリテラシーを使った例文>
「ビジネスリテラシーが備わったマーケティング担当者は、顧客のニーズを深く理解して、商品やサービスの提案を行うことができる」
「社員にビジネスリテラシーが備わっていると、部門間の連携がスムーズになり、チーム全体での目標達成がより効果的に進行する」
情報リテラシー
情報リテラシーとは、一般的に目的に応じてさまざまな情報から検索、収集を行い、適切に取捨選択して活用する能力や情報の真偽を見極められる能力のことです。現代ではインターネットを介して情報をやりとりするケースが多いため、ITリテラシーと同じような意味で使われることもあります。ただし、情報リテラシーの「情報」には、人との会話や手書きの文書などアナログな情報も含むのが一般的です。
世の中には、不正確な情報や明らかに間違っている情報もたくさん存在し、特にインターネット上ではその傾向が顕著です。情報リテラシーが高まると、目的に合った正確な情報だけを選んで活用する力の向上が期待できます。
情報リテラシーを使った例文は次のとおりです。
<情報リテラシーを使った例文>
「従業員の情報リテラシーが不足していると、最新の技術や業界トレンドに対する理解が乏しくなり、競合他社に対して競争力を失う」
「高度な情報リテラシーを持つ人材は、情報の信頼性をしっかり確認し、リスクを最小限に抑える」
メディアリテラシー
メディアリテラシーとは、新聞やテレビ、雑誌などさまざまなメディアから得られる情報を適切に取捨選択して活用する能力です。情報リテラシーと似ていますが、メディアリテラシーはメディアそのものに焦点を当て、情報リテラシーは情報全般の扱い方に重点を置くという違いがあります。
メディアリテラシーを高めることで、各メディアの違いや特性を十分理解できるようになるでしょう。また、メディアが流す情報の中に有益な情報のほか、真偽不明の情報やフェイクニュースが含まれていることも判断できるようになります。
メディアリテラシーを使った例文は次のとおりです。
<メディアリテラシーを使った例文>
「メディアリテラシーが低いと、ネット上に流布されているデマやフェイクニュースを簡単に信じてしまう」
「メディアリテラシーを高めることで、メディアの信頼性を適切に評価できるようになる」
金融リテラシー
金融リテラシーとは、金融商品や投資、資産運用など、お金に関する知識や能力を指す言葉です。日常生活におけるお金の使い方や家計管理だけでなく、金利やローンに関する知識も含みます。
金融リテラシーは、お金のトラブルを防ぐ意味でも重要な能力です。投資詐欺などの金融トラブルを回避するためにも、金融リテラシーを高めておくことをおすすめします。また、適切な財務管理と投資判断をするためにも、高い金融リテラシーが必要です。
金融リテラシーを使った例文は次のとおりです。
<金融リテラシーを使った例文>
「経営者は金融リテラシーとして最低限、自社が保険でカバーすべき事象(自然災害など)を理解しておく必要がある」
「経営者の金融リテラシー向上は、資金調達の選択肢を広げ、企業の成長戦略に大きく貢献する」
ITリテラシーが低い場合のデメリット
リテラシーはさまざまな分野で使われますが、一般的に、企業にとって重要なのはITリテラシーであり、従業員のITリテラシーが低いことによるデメリットもあります。
ここでは、ITリテラシーが低い場合の主なデメリットを3つ紹介します。
情報漏洩のリスクが高まる
従業員のITリテラシーが低いと、情報漏洩のリスクが高まる点がデメリットです。例えばUSBメモリーなど記憶媒体の紛失、メールの誤送信などによる情報漏洩が挙げられます。企業秘密や顧客情報が社外に漏洩してしまうなど、大きな問題へと発展してしまう可能性があるのです。
ITリテラシーの中でも、特にセキュリティの問題は、社外からの信用を大きく損ねるだけでなく、場合によっては損害賠償へとつながってしまうこともあります。一度低下した信用・信頼を回復させることは容易ではないため、注意が必要です。
一方で、従業員のITリテラシーが向上することで、情報漏洩のリスクが減り、トラブルや不祥事を回避できるでしょう。セキリュティの問題は一部の関係者だけでなく、情報を扱うすべての従業員に関わってくるため、全社的なITリテラシー向上が求められます。
情報格差が拡大する
従業員のITリテラシーが低いと、企業内で情報格差が拡大するというデメリットもあります。ITリテラシーは、現代では誰もが一定レベルを身につけておかなければならないスキルです。そのため日々の業務は、社内のほぼ全員が一定のITリテラシーを持っている前提で進められます。
ITリテラシーが低いと、「情報共有が遅れる」「そもそも情報共有ができない」といった問題が生じ、情報格差が大きくなります。結果として、業務上のトラブルやミスを引き起こす原因となってしまうのです。
一方で、従業員のITリテラシーを高めると、ITツールを使いこなすこともできるようになり、情報共有にかかる時間が短縮できるだけでなく、正確な情報が伝わりやすくなります。「一部の人だけが誤った情報を持っている」といった事態を避けられるようになるでしょう。
生産性が低下する
従業員のITリテラシーの低さは、企業の生産性にも大きく影響し、デメリットをもたらすため注意が必要です。例えば同じ業界で、ITツールを積極的に活用できる企業とそうでない企業を比べると、ITツールを活用できない企業のほうが、業務スピードや効率化の面から生産性が低下しやすくなります。
近年ではコロナ禍や人手不足をきっかけに、業務の効率化や生産性向上を目的としてITツールやシステムを導入する企業が増えています。しかし実際には、ITリテラシーが低いことで新たな取り組みがなかなか進まないケースもあるようです。
一方で、従業員のITリテラシーを向上させて社内システムやツールを活用すると、企業全体として業務効率化が図れ、作業時間の短縮やナレッジの共有などにより、生産性の向上につながります。
中小企業のデジタル化の現状
企業にとってITリテラシーは重要とされています。では中小企業のデジタル化の現状はどのくらい進んでいるのでしょうか。中小企業庁が公表している「2021年版 中小企業白書」によると、「アナログな文化・価値観が定着している」「明確な目的・目標が定まっていない」「組織のITリテラシーが不足している」など、デジタル化の推進に向けた課題が多く目立っていました。
しかし、「2023年版 中小企業白書」では、コロナ禍の影響もあり、デジタル化の取組段階が進展しています。ITリテラシーの必要性や、企業全体でITリテラシーを高めることの重要性が理解されつつあるようです。一方で、「費用の負担が大きい」「デジタル化を推進できる人材がいない」「どのように推進してよいか分からない」などの理由により、まだデジタル化に取り組めていない中小企業が存在することも事実であり、企業間で格差が広がりつつあります。
出典:「2021年版 中小企業白書(HTML版)」「2023年版 中小企業白書(HTML版)」中小企業庁
中小企業におけるITリテラシーの高め方
中小企業がデジタル化を進めるにあたり、課題のひとつが「組織のITリテラシーが不足している」でした。ここでは、ITリテラシーを高める方法を4つ紹介します。
上層部を含め企業全体で教育を受ける
ITリテラシーを高めるには、上層部を含め企業全体でITに関する教育を受け、デジタル化の意義やメリットを理解する必要があります。場合によっては、上層部の意識改革から始めなければならないケースもあるでしょう。
専門家に相談するのもひとつの方法です。中小企業庁は、ITに関する専門家の派遣やオンライン相談などの支援を行っています。状況に応じてうまく活用しましょう。
参考:「2024年度版中小企業施策利用ガイドブック」中小企業庁
組織体制を整備する
中小企業がITリテラシーを高める方法として、ITに精通している専門的な人材を確保するなど、組織体制を整備する施策が挙げられます。ただ、IT人材はIT専業の企業や大企業に流れてしまうことが多く、中小企業が確保することは難しいかもしれません。IT人材が内部にいない場合は、外部の専門家などに依頼して進めることも検討しましょう。
IT関連資格の取得を支援する
中小企業がITリテラシーを高めるには、IT関連資格の取得を支援することも大切です。IT関連の資格には、民間の資格や国家資格などさまざまあり、「ITパスポート」「基本情報処理技術者」「マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)」などが代表例です。
企業がこれらの資格取得に対して参考書や受験費用の補助をすることで、従業員の学習意欲を高め、ITリテラシーの高い人材を育成することにつながります。
IT化を支援するための補助金を活用する
中小企業がITリテラシーを高めるためには、社内のシステム環境整備が必要です。しかし、コストがかかるため、IT化を支援するための補助金の活用をおすすめします。中小企業庁は、中小企業のIT化を支援するため、補助金制度によるサポートも行っています。例えば、「IT導入補助金」は、中小企業が業務効率化やセキュリティ対策などに向けてITツールを導入する際の費用を支援する補助金です。
補助金を活用してITツール導入のハードルを下げることで、中小企業のITリテラシーの向上につながります。IT化を進める際は、国や自治体による支援や補助金制度があるかどうか確認し、うまく活用することもポイントです。
参考:「デジタル・IT化支援」中小企業庁
中小企業もリテラシーを高める取り組みを積極的に行おう
リテラシーとは、さまざまな分野において情報を理解し適切に活用する能力のこととして使われる言葉です。
ビジネスリテラシーや情報リテラシーなどがよく使われる用語ですが、中でもITリテラシーの向上は、中小企業にさまざまなメリットをもたらします。例えば、業務効率化や情報セキュリティリスクの低下、情報の正確性の担保などが挙げられます。
しかし実際には、「デジタル化を推進できる人材がいない」「ITツールの導入費用がネック」などの理由で、なかなか進んでいない中小企業が多いのも事実です。
補助金制度などをうまく活用しながら、ITリテラシーを高める施策に取り組んでみてはいかがでしょうか。
監修
三浦 高(みうら たかし)
中小企業診断士、1級販売士、起業コンサルタント®、ドリームゲートアドバイザー、産業能率大学兼任教員。V-Spirits総合研究所株式会社代表取締役。これまで創業補助金検査員・審査員を従事。V-Spiritsでは起業支援担当として年間約30件の起業・開業をサポートし、資金調達担当としてクライアントの補助金や融資の獲得を支援している。各種補助金と融資の累計獲得件数は各々350件を超える。
MKT-2025-501
「ここから変える。」メールマガジン
経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事