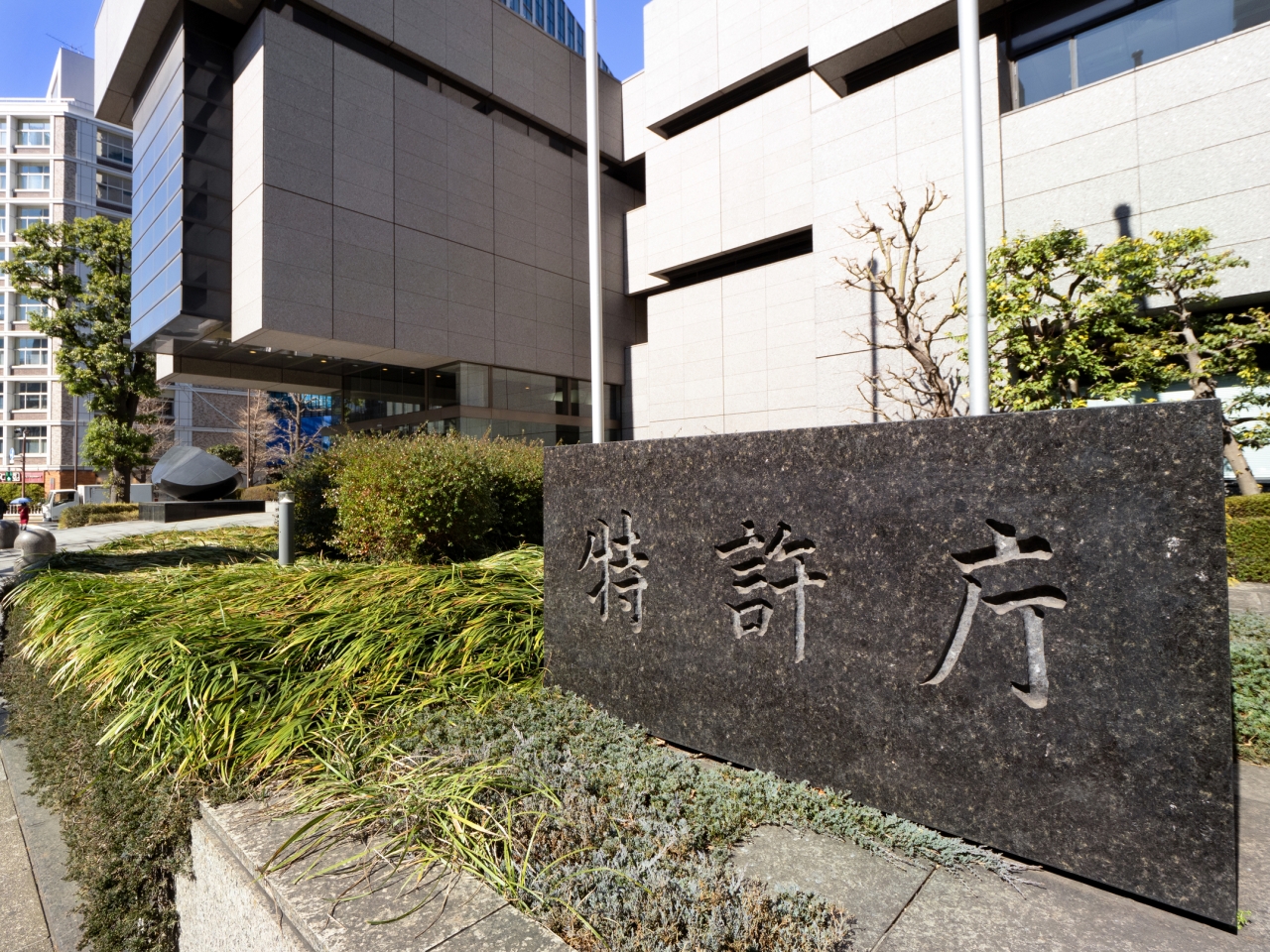-
ヒヤリハットとは、重大事故の予兆となる重要情報のこと -
ヒヤリハットとインシデント、アクシデント -
ヒヤリハットの重要性を示すハインリッヒの法則 -
ヒヤリハットの事例 -
ヒヤリハットが起きたときの対応 -
ヒヤリハットの事例を蓄積して重大事故を防ぐコツ -
重大な事故を防ぐためにも、ヒヤリハットの事例を有効に活用しよう
作業中に転倒しそうになったり、メールを誤って送信しそうになったりするなど、誰しも「ヒヤリとした」「ハッとした」という経験があるのではないでしょうか。些細なミスと見逃されがちですが、一歩間違えると労災事故や顧客との信頼関係の喪失につながるような事態になりかねません。
ここでは、ヒヤリハットの意味や事例、報告書の書き方、ヒヤリハットの事例を蓄積して重大事故を防ぐコツについて解説します。事故防止の取り組みを進めていきたいと考えている経営者は、ぜひ参考にしてください。
ヒヤリハットとは、重大事故の予兆となる重要情報のこと
ヒヤリハットとは、業務中に「ヒヤリとした」「ハッとした」など危険な事態が発生したものの、幸い大きな事故には至らなかった事象のことです。危機管理の観点でみると、重大事故の予兆となる重要な情報ともいえます。ここでいう重大事故とは、高所からの転落事故といった労働災害や、大きな損害となる設備の損傷、個人情報の大量流出など、企業活動や社会に大きな影響を及ぼす事態を指します。
ヒヤリハットがよく使われる業種としては、建設業や運送業、医療業などが挙げられますが、どのような企業でも日常的に起きている事象です。「大きな事故にならなくてよかった」で終わらせず、その経験を活かしてヒヤリハットの数を減らす努力が重要となります。
ヒヤリハットとインシデント、アクシデント
ヒヤリハットに似た言葉として、インシデントやアクシデントがあります。ここでは、「重大事故が発生」という軸を基準として、それぞれの違いは次のとおりです。
インシデントとヒヤリハットの違い
アクシデントとヒヤリハットの違い
アクシデントとは、予期せずに発生し、実際に重大な被害や影響を引き起こす事故や事件を指します。人や物への損害が発生し、即座に対応が求められる事態です。
例えば、工場での重大な機械トラブルや交通事故など、具体的な損害を伴うものがアクシデントに該当します。
一方、ヒヤリハットは、重大な事故やアクシデントに至る可能性があったものの、幸運にも実際の被害は発生しなかった状況を指します。
つまり、アクシデントは実際に損害が発生した出来事であるのに対して、ヒヤリハットは被害が発生していないものの、重大なリスクが認識された出来事を指します。
ヒヤリハットの重要性を示すハインリッヒの法則
ヒヤリハットの重要性を説明する際によく使われるのが、「ハインリッヒの法則」です。
ハインリッヒの法則とは、アメリカの損害保険会社に勤めていた安全技師・ハインリッヒ氏が発表した法則で、「同じ人間が起こした330件の災害のうち、重い災害が1件あったとすると、軽傷(応急手当だけで済む傷)が29件、傷害のない事故(ケガや物損の可能性があったヒヤリハット)が300件起こっている」という内容です。この数字から、「1:29:300の法則」とも呼ばれており、事故と災害の大きさについての関係を示す法則として、現在でも十分に活用できる考え方といわれています。
ハインリッヒの法則の本質は、「災害という事象の背景には、危険な要因(ヒヤリハットなど)が数多くある」「ヒヤリハットの情報をできるだけ把握し、スピーディーかつ的確に対応策を講ずることが大切」という点にあり、特に経営者はこの本質を理解しておくことが大切です。
■ハインリッヒの法則
参考:「職場のあんぜんサイト 安全衛生キーワード」(厚生労働省)
ヒヤリハットの事例
ヒヤリハットとは、具体的にどのような事象なのでしょうか。転落や転倒など、事故につながった可能性のある4つの事例を紹介します。
■ヒヤリハットの事例
事故の種類 |
事例 |
転落 |
テールゲートリフター(昇降機)に足を載せたとき、荷台とリフトの段差に気づかずにバランスを崩し、地面に転落しそうになった。 |
転倒 |
店員が、スーパーの外から店内のレジに走って戻ろうとしたとき、床が濡れており、滑って転倒しそうになった。 |
落下 |
作業員が、工事現場の足場を解体しているとき、足場材を取り外そうとしたところ、地上に落下させてしまった。落下防止ネットの一端が固定されていなかったため、足場材は道路まで落下し、歩行者にぶつかりそうになった。 |
個人情報漏洩 |
社員が、複数の顧客に対してイベントの案内を電子メールで送信しようとした際、本来はBCCにメールアドレスを入力すべきなのに、CCに入力して送信しそうになった。 |
出典:「職場のあんぜんサイト」(厚生労働省)「個人情報保護法 ヒヤリハット事例集」(個人情報保護委員会)
ヒヤリハットが起きたときの対応
現場でヒヤリハットが起きたとき、どのような流れで対応すればいいのでしょうか。基本的な対応を3つの段階に分けて解説します。
1 ヒヤリハット報告書の作成
まず、ヒヤリハットに特化した「ヒヤリハット報告書」を作成しましょう。
ヒヤリハットに遭遇した当事者は、ヒヤリハット報告書に当時の状況や原因、対策などを記載します。ヒヤリハット報告書を活用すれば、第三者に対しても客観的に伝えることが可能です。
また、内容を一覧化したファイルを作っておけば、過去に似たようなヒヤリハットがあったかなどの分析を行いやすくなります。
ヒヤリハット報告書は、発生した原因の検討や事故防止策を講じるための基本となる文書です。具体的には、下記のような5W1Hを意識した報告書を作成すると、内容がわかりやすくなり、抜けや漏れの防止につながります。
<ヒヤリハット報告書の基本事項>
・いつ(When):いつ発生したのか?
・どこで(Where):どこで発生したのか?
・誰が(Who):当事者、関係者は誰か?
・何をした(What):何が起こったのか?
・なぜ起きた(Why):なぜ発生したのか?背景や原因は?
・どうするか(How):どのように対処するのか?
2 原因の検討
ヒヤリハット報告書が提出されたら、安全管理の担当者は必ず内容を分析し、原因を検討しましょう。
1の報告書にも原因と対策を記載しますが、ここでは個人的な視点ではなく組織としての原因究明と対策策定を行います。情報共有と注意喚起のみで済ませてしまうと、従業員の安全に対する自発的な意識に頼ることになり、組織として重大事故を回避するという根本的な解決には至りません。
なお、原因を探る際、犯人探しや責任の所在を明確にすることが目的にならないように注意してください。
3 事故防止策の策定
ヒヤリハットの発生原因が明確になったら、どのように対処すべきだったのかを考え、具体的な改善策や事故防止策を策定しましょう。
いくらヒヤリハットに注意していても、時間が経つと意識が薄れて再発する可能性があります。従業員がそれぞれ、自発的にリスクを避けるような行動を取ることだけに期待するのではなく、ヒヤリハットが発生しない状態および環境をつくり出すことが重要です。
ヒヤリハットの事例を蓄積して重大事故を防ぐコツ
自社で起きたヒヤリハットの事例を蓄積し、そのデータを活用すれば、重大事故の防止につながります。そのためのコツを4つ紹介しましょう。
経営者がヒヤリハットの重要性を把握する
経営者は、ヒヤリハットの重要性を把握しておかなければなりません。
経営者は意識改革を図りつつ、自社におけるヒヤリハット事例の蓄積に向けて陣頭指揮をとりましょう。また、報告されたヒヤリハットを経営者みずからが確認し、リスクを低減するための対策を検討することも重要です。
ヒヤリハット報告書のフォーマットを作成する
ヒヤリハット報告書のフォーマットを作成し、従業員が簡単に報告できるような環境を作っておきましょう。
フォーマットは、5W1Hなどの基本事項をベースにして、自社に合わせたカスタマイズをします。記入項目を簡潔にする、記述式ではなく選択式にするなど、書きやすい工夫をすれば、報告者の手間を軽減できます。
報告しやすい環境づくりをする
従業員にとっては通常の業務がメインであるため、「ヒヤリハットについて報告する時間がない」「報告書の作成が面倒だ」という気持ちになりがちです。そのため、報告しやすい環境をつくることが大切です。例えば、朝礼や定例会などでヒヤリハット報告のための時間を設ける、といった施策が挙げられます。
また、「報告することで叱られてしまうのではないか?」と不安を抱き、積極的にヒヤリハットを報告しない従業員もいるかもしれません。それを避けるためには、報告してくれた従業員へ感謝の意を伝えることが大切です。そして、報告者からの報告を真摯に受け止める姿勢を見せるようにしましょう。報告によって、評価が下がることはないという明言も必要です。
仕組みづくりとしては、「ヒヤリハット報告による事故防止の成果によって、インセンティブ制度を設ける」「上司がまとめてヒヤリハットの報告をする」といった施策があります。
定期的な研修を行う
ヒヤリハットを活用して事故を防ぐためには、定期的な研修を行うことが重要です。研修を定期的に行うことで、従業員の危機意識低下を防ぎます。
ただし、一方的に講義を聞くだけの研修では効果が薄いため、より実践的な研修を実施しましょう。具体的には、「自社と同じ業種のヒヤリハット事例を集めて紹介し、当事者意識をもって捉えるようにする」「ワークショップ形式で、ヒヤリハットについて話し合ったり対策を考えたりする時間を設ける」といった内容が有効です。
重大な事故を防ぐためにも、ヒヤリハットの事例を有効に活用しよう
ヒヤリハットは、業務中に「ヒヤリとした」「ハッとした」という危険な状況が発生したものの、幸い大きな事故には至らなかった事象で、重大事故の予兆となる重要情報ともいえます。業種・業界を問わず発生する可能性があり、誰もが経験することでしょう。
ヒヤリハットには、重大事故の発生を防ぐためのヒントが隠されています。ヒヤリハットを有効活用したいと考えている経営者の方は、「ヒヤリハット報告書のフォーマットを作成する」「報告しやすい環境をつくる」「定期的に研修を実施する」といった取り組みを進めてみてはいかがでしょうか。
監修
三浦 高(みうら たかし)
中小企業診断士、1級販売士、起業コンサルタント®、ドリームゲートアドバイザー、産業能率大学兼任教員。V-Spirits総合研究所株式会社代表取締役。これまで創業補助金検査員・審査員を従事。V-Spiritsでは起業支援担当として年間約30件の起業・開業をサポートし、資金調達担当としてクライアントの補助金や融資の獲得を支援している。各種補助金と融資の累計獲得件数は各々350件を超える。
MKT-2025-505
「ここから変える。」メールマガジン
経営にまつわる課題、先駆者の事例などを定期的に配信しております。
ぜひ、お気軽にご登録ください。
関連記事
パンフレットのご請求はこちら
保険商品についてのご相談はこちらから。
地域別に最寄りの担当をご紹介いたします。
- おすすめ記事
- 新着記事