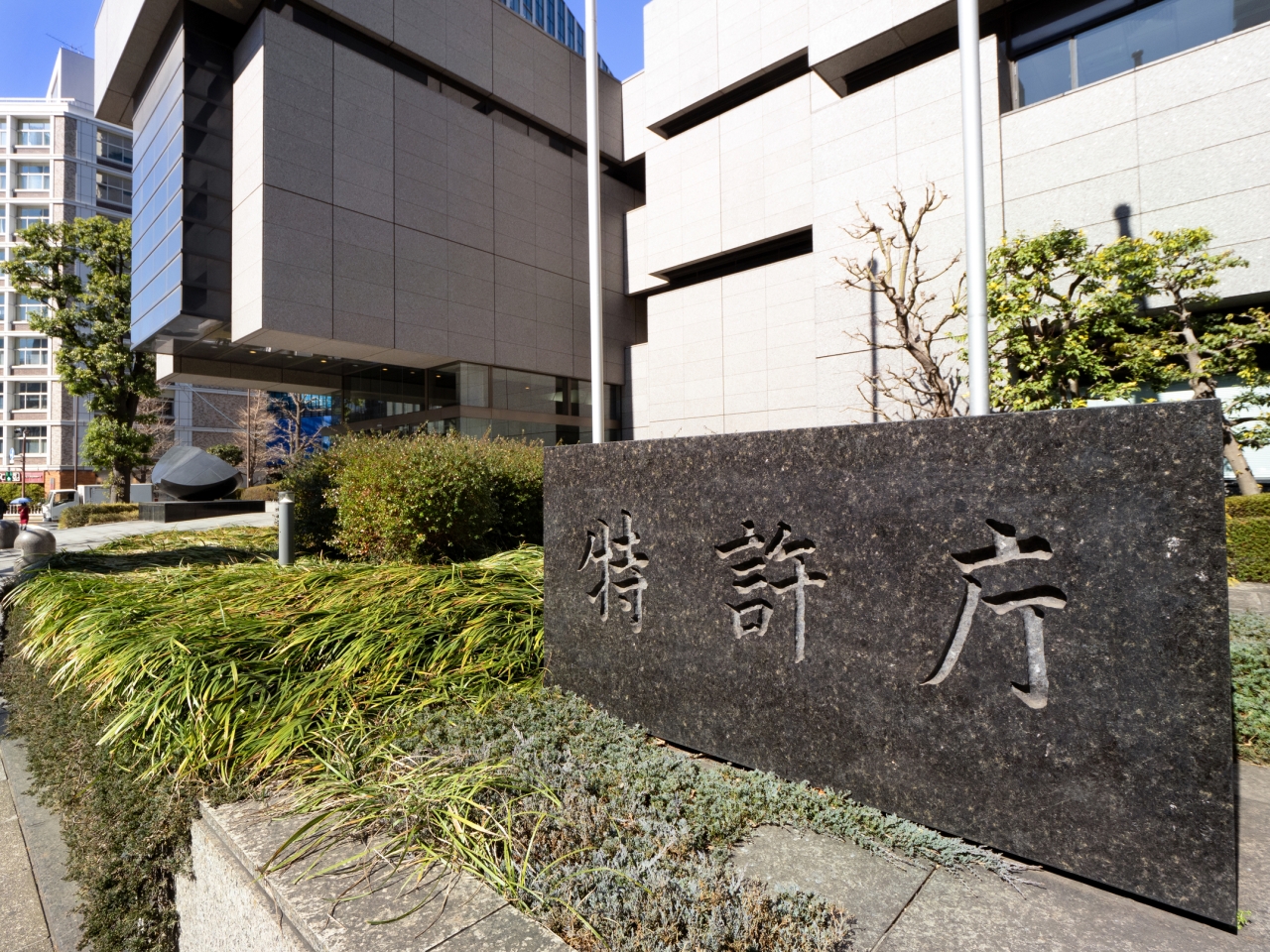車両管理とは
車両管理とは、企業や組織が業務に使用する車両を安全かつ効率的に管理することです。ドライバーや各車両を管理する日報の作成、車両の点検や整備、トラブルなど、さまざまな内容が含まれます。
企業が所有している車両だけではなく、リース車両に加え従業員が所有する車両であっても、業務に使用する場合は企業として管理する必要があるでしょう。
車両管理に必要な資格
車両管理にかかわる資格としては、「運行管理者」と「安全運転管理者」の2つがあります。
両者の違いを簡単に言うと、運行管理者はタクシーやトラックといった運送事業のいわゆる「緑ナンバー」の車両を管理する場合に必要な資格です。試験を受けて合格するか、5年以上の実務経験があれば講習を受講することで資格を取得できます。対して、安全運転管理者は試験のある資格ではなく、選任後、年に1回公安委員会が行う講習を受け、自家用車である「白ナンバー」を管理します。
運行管理者
運行管理者は、運送事業者である緑ナンバーの車両とドライバーの安全を管理、実施する担当者で、貨物と旅客の2種類があります。
公益財団法人 運行管理者試験センターが実施する試験に合格するか、運行管理の実務経験が5年以上あり、所定の講習を受講することで運行管理者となることができます。
例外はありますが、1つの事業所につき1人以上選任しなければなりません。1台から30台に1人、30台から59台で2人という具合に、30台増えるごとに1人ずつ必要人数が増えていきます。
安全運転管理者
安全運転管理者の役割は、事業主に代わって安全運転を確保することです。酒気帯び運転の確認やドライバーの状況把握、安全運転の指導といった業務を担います。
事業所として乗車定員11人以上の自動車を1台以上、そのほかの自動車を5台以上使用している場合に1人配置しなければなりません。また、20台以上になった場合は1人、以降20台増えるごとに1人の副安全運転管理者を選任する必要があります。
安全運転管理者(副を含む)を選任したら、15日以内に使用の本拠地を管轄する警察署を通じ、公安委員会に届け出を行います。選任された安全運転管理者(副を含む)は、年に1回公安委員会が実施する講習を受けなければなりません。
安全運転管理者については、下記記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
企業にとって車両管理が重要な理由とは
荷物や人を輸送する運送事業者ではなくとも、日々の業務を行う上で自動車が欠かせないという企業も多いでしょう。しかし、自動車を公道で走らせるということは、交通事故のリスクがあることを理解しておかなければなりません。
業務中の交通事故は、金銭的な損失を生むだけでなく、企業として社会的な信用を失う恐れがあります。車両の点検やメンテナンスはもちろん、車を運転する従業員(ドライバー)の健康管理や安全運転に対する意識など、細部にわたって管理することが必要です。
また、車両の点検や整備は、事故を未然に防ぐ上で有効な手段です。車両管理をしっかり行い事故のリスクを低く抑えることは、従業員の安全と企業の信頼を守ることに繋がります。
そして、業務に関連する車両の状態をしっかり管理することで、燃料代や保険料といったコストを見える化し、適正化する効果も期待できます。
車両管理で企業が行うべきこと
運行管理者や安全運転管理者といった担当者を選任する以外に、企業として車両管理を行う上でやるべきことがあります。ここからは特に、一般事業者向けに解説していきます。
それが、車両管理規程の作成と車両管理台帳の作成です。ここからは、それらについて解説していきます。
車両管理規程を作成する
車両管理規程とは、従業員が業務中に使う自動車に関して定めたルールのことです。企業として車両管理をしっかり行っていくため、車両管理規程の作成は欠かせません。
車両管理規程によって厳格なルールを定めることで、ドライバー(従業員)の安全運転に対する意識を高めることができます。
従業員の命を守るためにも、車両管理規程の作成は必須です。
車両管理台帳を作成する
業務に関連した自動車の台数が増えるほど、すべての車両の状況を管理することは困難になっていきます。そこで、管理者や経営層が車両の管理をしやすくするために必要となるのが車両管理台帳です。
車両管理台帳の作成には、エクセルやGoogleスプレッドシートなどを使用するといいでしょう。大きく「車両の特定」「車両の状況」「車両の保険」という3つの項目に分けて記載します。
車両管理台帳(記入例)
車両の特定 |
・車両メーカー ・ナンバープレートの番号 ・車体番号 ・カラー ・購入先やリース先 ・所有者(従業員の個人所有かどうかなど) |
車両の状況 |
・車検や点検の期日と実施状況 ・整備やメンテナンスの実施状況と費用 ・使用部署やドライバーなど |
車両の保険 |
・自賠責保険の有効期間と保険会社 ・証明書番号など ・任意保険の保険期間と保険会社 ・証券番号など |
これらの情報をひとまとめにしておくことで、1台ずつの状況を把握しやすくすることにつながります。タイヤの空気圧不足や灯火類の不点灯などの整備不良は、日常点検や定期的なメンテナンスで防ぐことが可能です。また、いつどんな整備やメンテナンスを実施したかを記録しておくことで掛かっているコストも可視化できます。
車両管理の担当者を選任し、設置する
企業として車両管理を確実に行うためには、担当者を選任して設置することが大切です。
車両の管理は多岐にわたるため、車両管理を行う専門部署を設置することが理想的ですが、運送事業者ではない一般企業ではあまり現実的ではありません。
そこで、車両管理にかかわる業務を細分化し各部署に分散しましょう。日々の運行管理や安全運転の教育は安全運転管理者、車両管理台帳の管理や従業員の免許証情報の把握は総務など、それぞれの部署に担当者をつけることで、効率的に管理できます。
担当者の業務とは
複数の部署や専任の担当者で車両管理を分担したとしても、やらなければならない業務が減るわけではありません。
例えば安全運転管理者の業務には、運転者の適性や技能の把握、安全運転の指導といった人の管理、車両管理台帳や日報、アルコールチェックといった日々の管理など、多くの業務があります。
アルコールチェックに関しては、2022年4月の法改正により運送事業者だけではなく業務に使用するすべての車両に対し、安全運転管理者による結果の記録と保存が義務化されました。
また2023年12月からはアルコールチェックに検知器を使用して行うこと、その検知器を常時有効に保持することが義務化されました。
企業にとって車両の管理は大切ですが、車両管理にかかわる業務の負担が増えているのも事実です。
アルコールチェック義務化については下記をご覧ください。
DX化やツールの導入を検討する
各車両を適正に管理し、企業の利益と従業員の安全を守るためには、車両管理の業務を効率化しつつ、担当者の負担を軽減することが効果的です。
そのために、車両管理にかかわる業務のDX化やツールの導入を検討しましょう。DX化やツールを導入することで、運行状況やアルコールチェックの記録と保存を簡単かつ確実に行うことが可能です。
また、より多くの情報を一元管理できるようになるため、担当者だけでなく管理職や経営層がいつでも確認しやすくなります。
日報とアルコールチェックのDXなら当社の日報アプリ
ここまでお話ししてきたように、車両管理においてポイントとなるのが、運転日報とアルコールチェックです。運転日報は、道路交通法により最低1年間の保存が義務付けられていますが、記録簿の提出や、集約作業、必要な記録の呼び出しなど業務が煩雑になる恐れがあります。
そこでおすすめしたいのが、「日報&アルコールチェック記録アプリ」です。
アプリでは、従業員はスマホを使って酒気帯び確認の記録や運転日報を入力することができ、入力された情報は管理者のPCで確認することができます。
入力は従業員が行うため、管理者の負担を軽減できます。また、運転免許証の有効期限や車両の予約情報も登録できるため、車両管理にかかわる業務の効率化が可能です。
車両稼働状況や位置情報を含めた車両管理ならテレマティクスの導入
安全運転管理者に課せられた、もう一つの大切な業務が、効率的な運行と安全運転の教育です。しかし、実際の運転は管理者がその目で確認することはできません。
そこで導入をおすすめしたいのが、テレマティクスサービスの「SuperDriveGuard※(以下SDG)」です。
SDGは専用端末を車両の点検コネクタ(OBDコネクタ)に設置するだけで利用でき、「可視化」「分析」「通知」という3つの領域で車両管理をサポートします。
※SuperDriveGuardは、AIG損害保険㈱の提携会社が提供するサービスです。
「可視化」では、運行ルートや速度を記録し運転日報として表示することができ、作成に掛かる手間を削減するとともに確実な記録を残すことが可能です。
次に「分析」では、アクセルの踏み方や速度などをスコアリングし、各ドライバーの運転の癖や特徴をフィードバック。数値として「見える化」することで、自分の運転を客観的に見ることができ、安全運転の意識を高める効果が期待できます。
そして「通知」は、ドライバーが危険な運転をすると、自動的に管理者へアラートメールが送信されます。それによって、実際には見ることができない運転状況を把握でき、荒い運転を行うドライバーには適切な指導をすることが可能です。
車両管理をDX化するメリット
新たなシステムの導入には、当然コストが掛かりますが、車両管理をDX化することで、導入コスト以上のメリットを得ることが可能です。
ここからは、車両管理のDX化で得られる代表的な4つのメリットをご紹介していきます。
従業員の負担を軽減できる
アルコールチェックや運転日報の記録と保存は車両管理の基本であるものの、現場の従業員にとって負担であることも事実です。実際の負担としてはたいしたことないように思えても、その小さな負担が記入漏れの原因になり、確実な車両管理の妨げとなります。
車両管理のDX化とツール導入は、管理する担当者と自動車を使用する従業員双方の負担を軽減し、管理業務を効率化します。
車両管理の担当者は、個々の車両データを包括的に取りまとめ、より効率的で安全な運用に向けて業務改善に取り組む。社用車で出かける営業スタッフは、本来の業務である営業活動に集中するなど、業務負担軽減と業務効率化に繋がります。
事故やトラブルの対応が素早くできる
企業や事業所から離れた場所で事故やトラブルが発生した場合においても、車両管理のDX化は非常に有効です。DX化によってトラブルが起きた場所や状況をリアルタイムで正確に把握できれば、素早い対処が可能となり、損失を最小限に抑えることができます。
そのためにも、位置情報を含めタイムリーに通知が受け取れるSDGのようなツールを上手に活用しましょう。
車両管理の担当者は、個々の車両データを包括的に取りまとめ、より効率的で安全な運用に向けて業務改善に取り組む。社用車で出かける営業スタッフは、本来の業務である営業活動に集中するなど、業務負担軽減と業務効率化に繋がります。
運転状況を正確に把握することでコストを最適化
車両管理のDX化は、コストの最適化と削減に繋がります。
SDGを活用することによって、急加速や制限速度超過といった危険な運転をしていないか、ドライバーの運転状況を把握可能です。
無駄なアクセルと過度なスピードは、燃費を低下させる大きな要因になります。運転状況を正確に把握することで、安全運転の指導に役立てることができるのです。
また、DX化によって日々の運行状況を把握すれば、業務に必要な台数を明確にできます。稼働の少ない車両を把握することで効率的な運行管理を実現し、余剰車両を削減することでコストの圧縮も期待できます。
車両管理の改善と最適化ができる
車両管理は、担当者を付けてDX化することで改善と最適化がしやすくなります。
記録をつける作業をドライバーなど「人」に委ねると、記入漏れや誤記が発生し、正確な記録を取れなくなってしまいます。車両管理がおざなりになるのは、こうしたことが原因のひとつとして考えられます。
しかしテレマティクスサービスのSDGを活用すれば、距離や日時は自動で記録されるため、記入漏れは発生しません。また、そこで得られたデータを一元管理し、運行管理の担当者が取りまとめることで、車両管理を効率化するとともに最適化に向けた改善に取り組みやすくなります。
まとめ
人や物を運ぶ運送事業者はもちろんのこと、営業活動や自社製品の配達などに車両は欠かせない存在です。しかし、車両の維持にコストが掛かるのはもちろん、公道を走る以上、交通事故のリスクを避けることはできません。
コストを圧縮し、交通事故のリスクを軽減させるためには、適切な車両管理が不可欠です。
日々の業務負担を軽減しつつ、車両管理を確実に実施継続していくため、DX化とツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
執筆者プロフィール:
増田真吾
元自動車整備士ライター
国産車ディーラー、車検工場でおよそ15年自動車整備士として勤務したのち、大手中古車販売店の本部業務を経て、急転直下で独立しフリーの自動車ライターに転身。国家資格整備士と自動車検査員資格を保有し、レースから整備、車検、中古車、そしてメカニカルな分野まで幅広い知見を持つ。